
施工管理とは、建設現場、建築現場などで工事が始まる前から施工計画を立てて、工事が竣工(出来上がる)するまでのスケジュール管理やお金の管理、工程が順調に進んでいるかの管理やしっかりした製品ができているか(品質)を確認することが大きな仕事内容です。
近年では、『施工管理はきついからやめとけ。』『施工管理は長時間労働だから今の若い子には無理』などとネットでよく見かけますが本当にそうなのでしょうか?
施工管理をやってきた私が実体験を元に『施工管理』の実態を赤裸々に紹介します。
意外に多い施工管理の7つのジャンルと平均月収

一概に施工管理と言っても意外とたくさんのジャンル(種類)があります。その種類を施工管理の資格を元に紹介します。
また、各施工管理での平均年収も紹介します。施工管理の年収は資格の有無により大きく差が出る傾向にあります。上手に出世できれば1,000万円以上も稼げる夢のような仕事だと思います。
1、建築施工管理
建築施工管理とは、一般住宅、アパート、ビルや商業施設、工場などの大枠を建てる建設工事の管理を行う仕事です。
平均年収 480万円~780万円
2、土木施工管理
土木施工管理とは、道路、橋梁(きょうりょう)・河川・ダム・砂防・上下水道、下水処理場・トンネル、港湾、空港整備・土地造成、宅地開発など「インフラ」に関する土木の管理を行う仕事です。
平均年収 530万円~720万円
3、電気工事施工管理
電気工事施工管理とは、屋内、屋外、照明・コンセント・スイッチ類・電源設備(配電盤、受変電設備)・LAN・防災・放送・監視カメラなどの弱電設備・太陽光発電や蓄電池システムなどの省エネ設備・送電線などの電気工事の管理を行う仕事です。
平均年収 500万円~950万円
4、管工事施工管理
管工事施工管理とは、建物や施設に必要な給水・排水・給湯管工事空調配管(冷媒配管など)、換気ダクト工事、消火設備(スプリンクラーなど)ガス配管設備地中埋設配管工事など管工事の管理を行う仕事です。
平均年収 532万円~772万円
5、造園施工管理
造園施工管理とは、公園、緑地整備・街路樹・並木道の整備・商業施設の屋上緑化・壁面緑化・学校・病院の庭園・寺社仏閣や日本庭園の整備・公共工事における景観設計(道路・ダム周辺など)などの造園の管理を行う仕事です。
平均年収 480万円~700万円
6、建設機械施工管理
建設機械施工管理とは、建設現場で使用される重機や建設機械(クレーン、ブルドーザー、ショベルカー、フォークリフトなど)を管理・運用する仕事です。
主にクレーン(高所作業、重いものの運搬)・ブルドーザー(土砂の移動・整地)・ショベルカー(掘削作業)・フォークリフト(資材の積み下ろし)・ミキサー車(コンクリートの運搬)・アスファルトフィニッシャー(アスファルト舗装)・ロードローラー(道路舗装の圧縮)など工事現場で使う機械の管理を行います。
平均年収 400万円~800万円
7、電気通信施工管理
電気通信施工管理とは、電気通信工事において、通信ケーブルの敷設(光ファイバー、銅線など)・通信機器の設置(ルーター、スイッチ、基地局など)・無線通信インフラの整備(基地局の設置、無線LANの導入)・データセンターの建設や改修・通信回線の工事(企業向け、一般家庭向けの回線設置)など通信ネットワークを構築するための電気通信工事の管理を行う仕事です。
平均年収 441万円~725万円
意外に単純!?施工管理の仕事内容4選

施工管理の仕事内容は大きく分け『工程管理』、『品質管理』、『安全管理』、『原価管理』の4つに分類されます。4つの管理項目について詳しく紹介します。
施工管理の仕事は大変だというイメージが非常に強いと思いますが、実際に現場でやってみると単純で毎日が繰り返し作業になるので慣れればそれほど苦にはならない仕事内容だと私は思います。
1. 工程管理
施工管理における工程管理とは、予定通りに工事が進捗しているかを管理・調整する業務です。
一般的に工事全体の工程を一番最初に計画し、その工程通りに工事が進んでいるか、遅れている場合には原因を追究し予定の工程に乗せる作業になります。そして、スタートからゴールまでのペース配分を行い、各作業工程にて予定通りに行わせることが重要です。
作業工程の計画立案
送電線建設工事の場合、全体の工期(たとえば「12ヶ月で完成」)を基に、「基礎工事→組立工事→架線工事→付帯工事」といった作業順序を決め、スケジュール表(工程表)を作成。
進捗確認
現場で進捗状況を各工種ごと、毎日・毎週チェックし、計画との差を把握。
遅延の調整
天候、資材の遅れ、人手不足などで予定より遅れることも多いため、工種の前倒し・同時進行・休日出勤などでスケジュールを調整。
関係業者との調整
基礎工事、組立工事、架線工事などの作業タイミングが重ならないように調整し、無駄なく安全に作業を進める。(その他準備工、仮設足場、仮設工事などの調整)
スケジュール管理を職人と密に行い、遅延なく仕事を遂行することが工程管理の肝です。
2. 品質管理
施工管理における品質管理とは、建設工事の成果物(建物や構造物など)が、設計図書や仕様書に定められた品質基準を満たすように管理・確認・記録することです。
設計通りの品質を確保する、使用材料の品質を確認・記録する、施工手順・方法が適正であることを確認する、完成後の性能(耐久性、安全性、美観など)を担保することが具体的内容です。
材料の検査
コンクリートや鉄筋、材料などが規格通りかミルシートや受入検査にて確認を行う。
規定外や不備がある場合は、交換等の対処を行うことが必要です。
施工の検査
基礎工事の場合、掘削深さや幅が適正であるか、鉄筋が仕様書通りに配置されているか、 コンクリートのスランプ、空気量、温度などが適性値であるか、各工程の出来形や手順をチェックする。
記録の管理
各工種ごとに検査記録、写真、試験成績表などの書類を整備し、後で検証可能な状態にする。
外注・職人への指導
施工方法や精度の基準を職人や協力会社に指示し、教育・是正を行う。
3. 安全管理
施工管理における安全管理とは、建設工事の現場で働くすべての人の命や健康を守るために、事故や災害を未然に防ぐ管理活動です。安全はすべてに優先するとされ、「ゼロ災害(無事故・無災害)」を目指して継続的に取り組むべき最重要項目の一つです。
主に、労働災害(転落・墜落・挟まれ・感電・熱中症など)の防止、安全な作業環境の確保(整理整頓・動線管理・警告表示など)、法令遵守(労働安全衛生法など)、社会的信頼の確保(企業の責任・信用問題)等を行います。
リスクアセスメント
作業前に危険ポイントを洗い出し、対策を講じる。
過去の災害事例をもとに、今日行う作業に対しての危険ポイントを全作業員で確認する。
KY活動(危険予知活動)
作業前ミーティングで、当日の危険要因と対策を共有。
リスクアセスメント同様に、過去の災害事例等を活用し、今日の作業場所、作業状況に危険が潜んでいないか、危険がある場合、どのように対処するかの打ち合わせ。
保護具の使用
ヘルメット、安全帯、安全靴、手袋などの着用確認。
作業毎に、安全衛生法で定められた保護具着用を確認します。これを怠ると法律で罰せられることがあるので要注意です。また、保護具の付着用は命の危険にもなりかねないので、安全管理でとても重要な項目です。
足場・仮設の安全確認
足場・はしごの強度・手すり・転落防止措置の確認。
足場の適正配置や間隔、はしごの強度計算、手すりの高さなども安衛法で定められた既定の高さがあるので、許容ないに入っているかを確認します。
重機作業の安全対策
接触防止、誘導員配置、作業範囲の明示など。
重機(バックホウ、ブルドーザー、不整地運搬車など)車両系建設機械と呼ばれる機械に対して、作業員が近づかないように作業範囲の確認・明示、重機の誘導員の配置計画などを行います。
安全標識・掲示の設置
注意喚起の表示や掲示板で意識づけ
立入禁止、キケン、路肩注意、開口部安全帯使用などの注意喚起の標識等を配置し、作業員の誰が見てもわかるように注意喚起します。
定期的な安全パトロール
現場を巡回して不安全行動や不具合をチェック
毎日現場巡視を行い、危険個所、危険状態などを確認し危険な場合は即座に注意し是正します。作業員は作業に集中するあまり、見えない部分があるので注意が必要です。
また、現場では作業員とのコミュニケーションをとるいい場所です。コミュニケーションを深めることにより、何でも話せるいい環境作りができます。
安全教育・訓練
新規入場者教育、特別教育、安全講習会などの実施
4. 原価管理
施工管理における「原価管理」とは、工事にかかる費用(原価)を計画通りにコントロールし、適正な利益を確保するための管理活動です。工事が赤字にならないように、予算(見積)と実際のコストを比較・分析し、必要に応じて対策を講じることが中心です。
原価計画の立案
見積書や実行予算書をもとに、工種別・項目別の費用を計画
実行予算の作成
実際に工事で使用する材料・人件費・外注費などの予算を具体化
原価の記録・管理
材料費、労務費、外注費、間接費などを日々記録し集計
実績と予算の比較(差異分析)
実際の支出と予算の差を定期的にチェックし、要因分析を行う
コストダウン対策
無駄な作業・材料の見直し、施工手順の工夫による原価削減
報告と是正
毎月の原価報告書を作成し、赤字要因への対策を実行
施工管理の魅力とは!?やりがいはあるのか?

施工管理の魅力は、「自分の手で街をつくる」「形に残る仕事ができる」という大きな達成感と社会的意義にあります。また、技術・マネジメント・人間関係など幅広い力が磨かれる職業でもあります。
また、経済的にも豊かになれる可能性が高い職種です。冒頭で解説したように、施工管理の平均年収はおおよそ600万円を超えてきます。経験年数や資格の有無で変わってきますが、一般的な仕事より高収入を得ることが可能です。私のいる会社では1,000万円以上稼いでいる人が多くいる夢の会社です。
近年では労働時間の減少、休日の確保など、とても働きやすい仕事環境だと思います。
- 建物やインフラが「目に見える形」で残る
道路、橋、ビル、住宅など、自分が関わったものが長く人々の生活を支える。
完成したときの「達成感」は格別。家族や友人に自慢できる。
- プロジェクト全体を動かす「現場の司令塔」
設計、工程、安全、品質、原価を管理する多才な役割。
職人・技術者・協力会社とのチームワークが不可欠で、人を動かす力が養われる。
- 毎日が同じじゃない「変化に富んだ仕事」
デスクワークだけでなく現場に出る仕事で、日々の発見や課題がある。
工事の進捗に応じてやることが変わり、ルーティンにならない。
- 成長を実感しやすい環境
一つの工事ごとに知識やスキルが着実に増える。
資格取得(施工管理技士など)やキャリアアップが明確に目指せる。
- 社会貢献度が高い
災害復旧・インフラ整備・公共施設の建設など、人々の暮らしに直接影響する。
「安全な街」「快適な生活」を支える裏方としての誇りがある。
施工管理で必要な資格

施工管理に必要な資格は、工事の種類や規模に応じて変わりますが、中心となるのは「施工管理技士」資格です。これは国家資格で、現場の主任技術者や監理技術者として働くために必要です。
また、上級の資格をもっているほど給料にも反映することが多いです。資格取得にはそれなりの勉強が必要ですが思いのほか容易に取得できると思います。
1級施工管理技士
大規模・重要な工事 国家資格。監理技術者になれる。実務経験が必要。
資格取得は2級を取得しなくてもいきなり1級からチャレンジできる(オススメ)
1級を持っていれば2級のできることを網羅できる。
1級施工管理を取得するとできること
監理技術者になれる 特定建設業(大規模下請)では、1級施工管理技士と実務経験がある人しかなれない。現場の総責任者的な立場。
主任技術者として配置される 一般建設業の現場で、技術者として法的に配置できる。中小〜大規模すべての工事で有効。
国・自治体の入札参加資格(経審)で有利 技術者として加点対象。技術点を上げるために会社からも重宝される。
工事全体のマネジメントを任される 品質・工程・安全・原価の全てを管理する立場になれる。
昇進・給与アップ 現場代理人や工事長、所長、部長級への昇進が可能に。
独立・転職で有利 ゼネコン・サブコン・公務員(技術職)など幅広く活かせる。
教育・指導ができる立場 後輩技術者の育成や指導を任されることも多い。
2級施工管理技士
2級施工管理技士は、中小規模の工事や特定の分野の現場で主任技術者として従事できる国家資格です。1級に比べて扱える工事の規模や役割に制限はありますが、施工管理のプロとしての第一歩となる重要な資格です。
2級施工管理を取得するとできること
主任技術者として配置される 一般建設業の元請・下請の現場において「主任技術者」になれる(工事規模に制限あり)。
中小規模の工事を管理できる 住宅、事務所、店舗、公共施設、インフラの一部などの施工管理が可能。
発注者・設計者と打合せを行い現場を動かす 小規模現場では現場代理人(実質的な責任者)としての役割も担える。
現場での施工計画・品質・安全・工程管理を行う 実務は1級と大きく変わらない(ただし法的責任の幅に違いあり)。
1級施工管理技士の受験資格になる 実務経験を積めば1級にステップアップできる。
就職・転職で有利になる 中小ゼネコン、設備会社、リフォーム業などでニーズが高い。
監理技術者資格者証
監理技術者は、特定建設業の元請業者が、一定以上の規模の下請契約を伴う工事を行う際に、現場に配置しなければならない技術責任者です。主に1級施工管理技士 + 実務経験で取得でき、法律上の義務がある重要な立場です。
監理技術者を取得するとできること
特定建設業の「監理技術者」として現場に配置される 下請契約金額が7000万円以上(建築一式なら6000万円以上)の工事に、必ず配置が必要(建設業法 第26条)。
元請として大規模な公共工事を受注できる 監理技術者の有無が、入札要件に含まれる自治体・国の案件も多い。
現場全体の技術管理・下請指導ができる 複数の下請業者を束ねて、品質・工程・安全を総合的に管理。
技術的な窓口・交渉役になれる 発注者・設計者・行政との技術的調整の主担当となる。
施工体制台帳・再下請通知などの技術管理書類を扱える 技術的責任者として、工事の法的書類や管理を行う。
施工管理に必要な能力
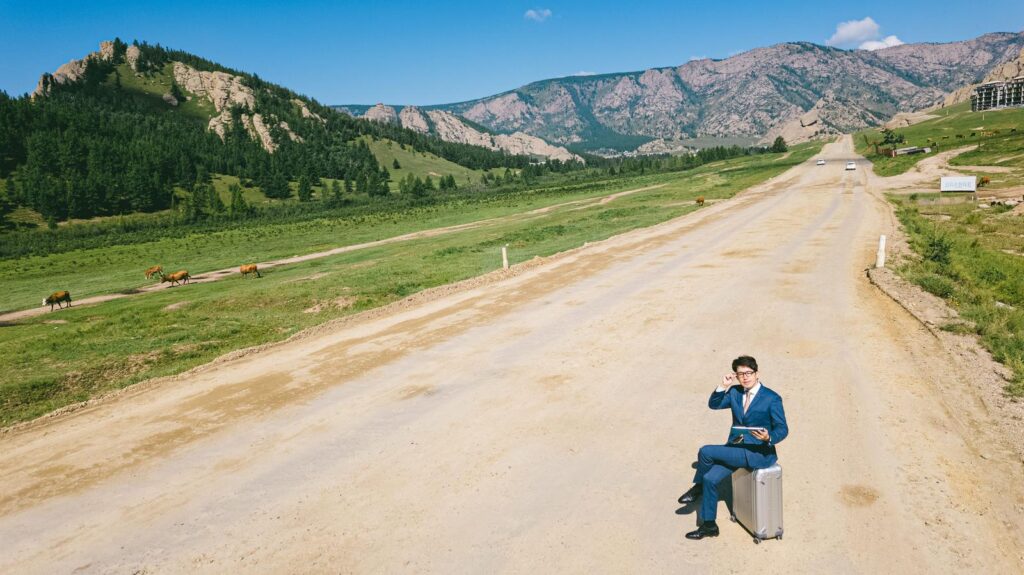
施工管理に必要な能力は、単に「建設の知識」だけではありません。技術力・マネジメント力・コミュニケーション力を総合的に備えた「現場の司令塔」としての能力が求められます。
特にコミュニケーション能力が重要です。いくら知識があっても職人とのコミュニケーションが取れなければ力を十分に発揮できません。
また、職人から聞かれたことに対しての対応力も必須です。そのために、知識を学ぶ勉強も大事です。
1. 技術的知識と判断力
- 設計図や仕様書の理解力(建築・土木・設備など)
- 施工方法・工法・材料の知識
- 品質・安全・工程に関する基準の理解
- 法令・基準の知識(建築基準法、労働安全衛生法など)
- 現場での不具合やトラブルへの技術的対応力
2. 計画力・段取り力
- 工程表の作成・進捗管理
- 作業順序や工種ごとの段取り(施工計画)
- 必要資材・人員の発注や手配のタイミング管理
- 限られた期間・予算の中で最大の成果を出す力
3. コミュニケーション力
- 職人・協力会社との調整・指示・信頼関係構築
- 発注者や設計事務所との折衝・報告
- 現場でのトラブル回避・現場全体の雰囲気づくり
- チーム全体をまとめる「リーダーシップ」
4. 管理能力
- 安全管理:KY活動、パトロール、安全教育
- 品質管理:検査・記録・写真などの対応
- 原価管理:予算・実績の記録と分析
- 書類管理:報告書・台帳・契約書類の整理と提出
5. IT・デジタルリテラシー
- CAD図面や施工管理ソフト(例:BIM、Revit、Excel、現場クラウドなど)
- 写真・報告書の電子化対応
- ドローン・3Dスキャン・IoTなど新技術の活用意欲
6. 冷静な判断力とストレス耐性
- 多忙な中でも冷静に判断し、周囲に安心感を与える
- 天候・トラブル・急な変更にも柔軟に対応
- プレッシャーに強く、責任感を持って業務を遂行する
7. 学び続ける姿勢
- 資格取得(施工管理技士、建築士など)
- 新しい施工技術・法改正への対応
- 現場での経験を次に活かす「振り返り」の習慣
まとめ 施工管理になるためのおすすめ方法

施工管理は、高卒や大卒でも就職は可能です。しかし、作業に対しての知識が全くない状態からスタートするので職人さんとのコミュニケーションはなかなか厳しいものがあります。
そこで私がオススメする方法が職人から施工管理への転職です。私自身、職人を12年間行い、その後施工管理へと転職しました。職人を長く経験していると作業への知識も豊富で職人との会話もスムーズに行うことができました。職人からの罵声に対しても昔自分もこんなこと言ってたな。ぐらいで動揺しません。
また、資格有(1級電気施工管理技士・監理技術者)での転職だったため、管理の経験はないにしろ、ある程度厚待遇で入社することができ、年収も前職の2倍になりました。
私の経験から、職人から施工管理に転職することをお勧めします。


コメント